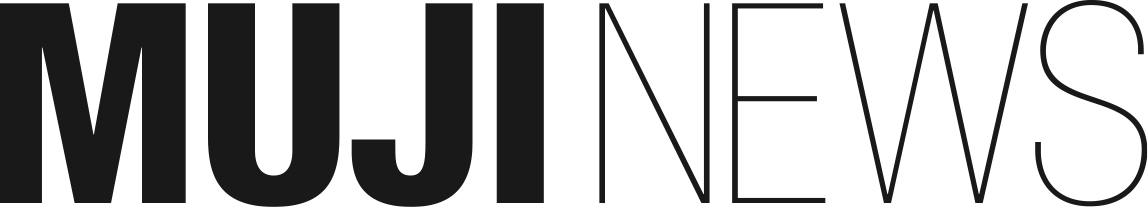ソーシャルグッド事業部 鈴木 恵一さん
現在北海道地域の推進を担当している鈴木さんは、夕張市役所と連携した植栽バスツアーの企画開催や、地域の高校生との交流などを通して、北海道の過疎地域を中心に地域のつながりを再構築するための活動を行っています。これまでに行ってきた活動や心がけていることについてお話を伺いました。
■これまでに行ってきた活動
私は1988年から無印良品で勤務しており、販売部のほか、くらしの良品研究所などに所属してきました。定年まであと数年となったときに、「生まれ育った地域の方々の役に立つことをしてみたらどうか」と金井さんがおっしゃってくださったことがきっかけで2013年に故郷の札幌に戻り、トークイベントを通して地域を紹介する活動をはじめたのがスタートです。無印良品 札幌ステラプレイスを拠点に2013年から年3~4回のペースでイベントを実施してきました。
その活動を続けていく中で、「夕張の力になるために何かできないか」という話が上がりました。かつては炭鉱の町として栄えた北海道夕張市ですが、2007年に財政破綻を表明して以降、厳しい財政状態が続いています。そこで、2017年に当時夕張市長だった鈴木直道氏らを迎え、無印良品 札幌ステラプレイスでトークイベントを開催し、次の年の2018年5月には夕張市が舞台の映画「幸福(しあわせ)の黄色いハンカチ」にちなんだ、当社主催による植栽バスツアーを実施しました。このイベントはその後も継続的に実施しており、関係人口をつくることや、地域に住む方々が自分ごととして地域の課題を考えるきっかけとなっています。
■未来の担い手となる高校生との交流
7月下旬、北海道河東郡にある鹿追高校の「総合的な探求の時間」の授業に講師としてお招きいただき、アートデザインについての講義を行いました。鹿追高校ではアクティブラーニングで答えを導きだす課題解決型の授業を積極的に行っており、この授業では地域のキーマンとどういうことができるかを高校生が議論し、解決策をまとめ、来年1月に最終発表を行います。私の他にも、観光やスポーツ、看護・医療といった各分野の専門家が講師として参加しており、鹿追高校の生徒と一緒にこの地域の未来について考えていきます。
この授業の仕掛人である俵谷校長は、前任が奥尻高校でした。奥尻島は北海道南西部の日本海上に浮かぶ人口約2,600人の小さな島で、縄文時代の遺跡や遺物が多く見られる歴史のある島です。離島では、学校がなくなると地元で進学することが難しくなってしまうため少子高齢化が一気に加速してしまいます。いかに自分たちの島に学校を残すかということが死活問題なのですが、俵谷校長は奥尻島に高校を残すために尽力した方です。これまでに北海道で活動していく中で俵谷校長とつながり、ローカルニッポンでの紹介や「つながる市」などのイベントを通して奥尻高校の生徒との交流を深めてきたご縁があり、今回もそのつながりの中でお声掛けいただきました。
高校生や大学生など、これからを担う若い人達の中には「自分が生まれ育った地域をなんとかしたい」と思ってくれている人がたくさんいます。元気なエリアの特長は、もともと住んでいた人達と新しい人達が融合していることだと思いますし、地元のために何かをしたいと言ってくれている学生達と一緒に悩み、考え、行動していくことで、地域は少しずつ変わっていくのではないかと思っています。
■大切にしていること
すべての地域活動に言えることですが、地域のいろいろな方と話をし、足を運び、課題を共有することが大切です。私は、地域が活性化するためのお手伝いをする際に、「風の人」「土の人」という言葉を使っています。土の人とはもともとその土地に住んでいた人、風の人とは縁あって移住してきた人や、関係人口のことを指しており、風と土とが混ざり合って融合するとそこに新しい「風土」ができると信じています。無印良品だけで地域の役に立つことはできません。外から来た人だけが何か新しいことをやるのではなく、地を盛り上げるために頑張っていきたいと思っている人を見つけ出したり、未来の担い手となる学生と話すことがとても重要だと考えています。
9月からは、無印良品 札幌パルコの土着化担当として着任することになりました。地域で活動する方々とお客様をつなげる「つながる市」を通して地域活性化のお手伝いをしていくとともに、自治体や他企業との連携し、北海道で頑張ろうとしている若い方々と一緒に地域を盛り上げていきたいです。